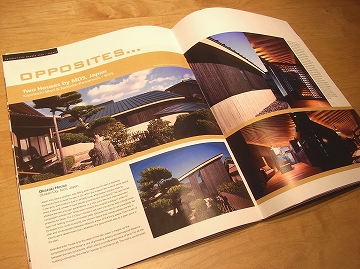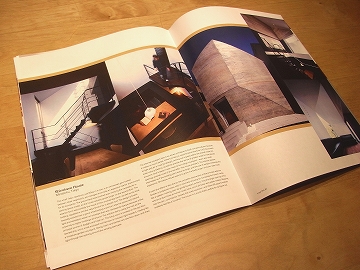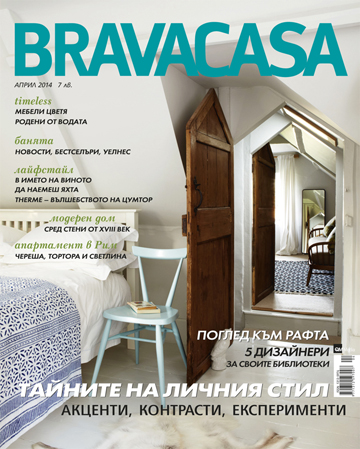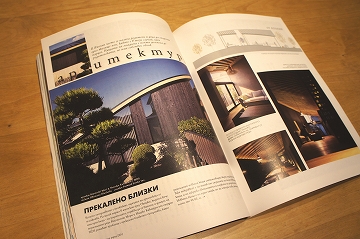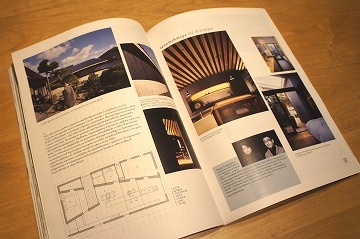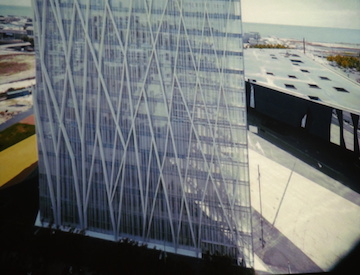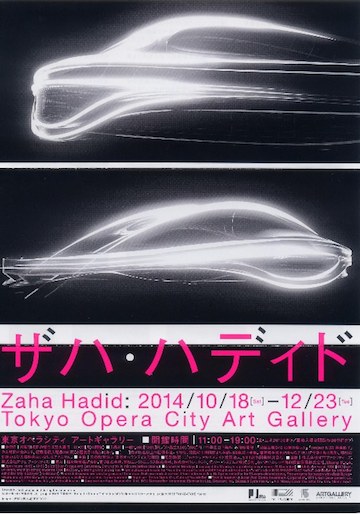今日は東京理科大学の今年最後の授業。
ゲスト講師として坂本一成先生をお呼びした全体講評会なので、
やや緊張しながらもとても楽しみにして大学に行ってみると、
EMBAの ENRIC MASSIP-BOSCH氏とELVで偶然一緒となり、
どうやら講演していただけるとのこと。
バルセロナ大学でも教鞭をとられている建築家なのですが、
東京工業大学の篠原研究室の留学生だったらしく、
坂本先生ともつながっているようでした。
ということで、急遽、講評会の前に1時間程のご講演して頂きました。
随分と豪華な授業になりました。
英語での講演でしたが、サクラダファミリア周辺のプロジェクトや、
海沿いに建つ集合住宅など、とても魅力的なものでした。
バルセロナは学生の時に一度だけ行ったことがありますが、
新旧が混ざり合った魅力的な街で、
また、近々に行って見たくなるようなレクチャーでした。
その後、坂本先生を交えて、設計製図の全体講評会。
学生に丁寧にコメントする坂本先生に、
我々の指導方法も講評していただいている感じでした(笑)。
全体講評会の後は、学生と打ち上げ、
しばらくして、坂本先生と講師だけは場所を変えて、夜遅くまで建築談義。
とても充実した一日でした。