
MDSが設計した、 Hat on the Ridge にて、3/7(土)から3/22(日)まで 友人の 五月女 寛 さんの作品展示が行われます。写真は今回の展示のためにお預かりした作品写真。 Quadrivium Ostium は本格的にギャラリーとして活動を始められるということで、今後の展開が大変楽しみです。ぜひ足を運んでみてください。
―展示概要
2026 年 3 月 7 日(土)~3 月 22 日(日)
会期中予約不要
会期中休:3 月 10、11、12、16、17 日
作家在廊日:3 月 7、8、20、21、22 日
営業時間:11 時~17 時
展示の詳細は、ギャラリーのInstagram からご覧ください。
作家・五月女 寛 のInstagramは コチラ







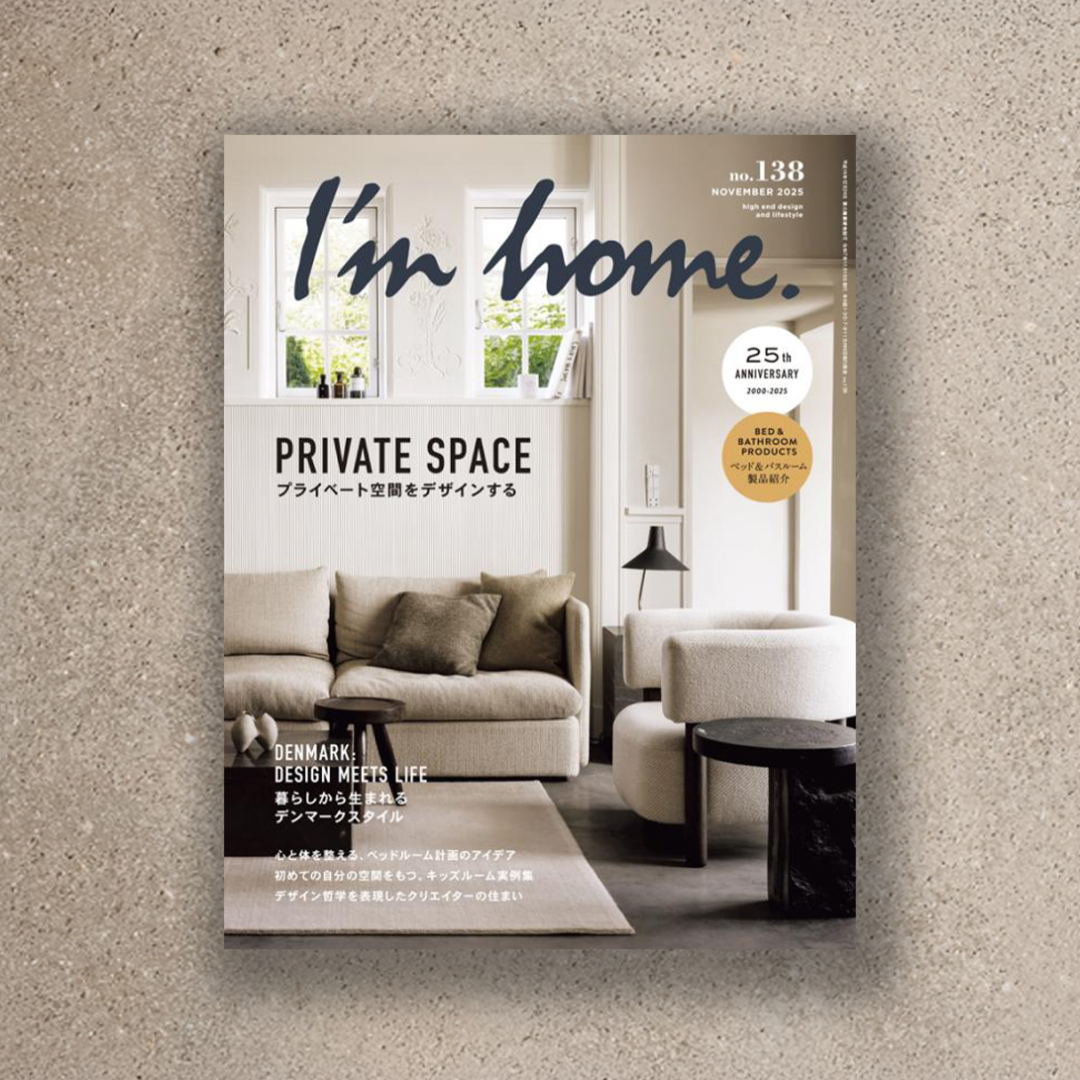














 >暮らしの空間デザイン手帖/改訂版
>暮らしの空間デザイン手帖/改訂版 >暮らしの空間デザイン手帖
>暮らしの空間デザイン手帖 >日本建築師才懂の思考&設計/台湾
>日本建築師才懂の思考&設計/台湾