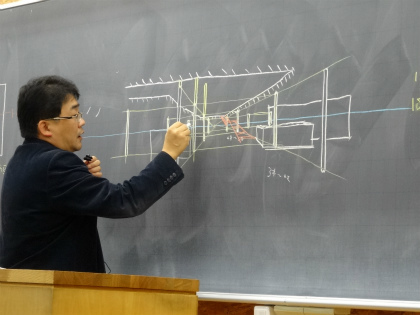東京都の方に伐採現場およびその関連施設を案内していただきました。
ところで、
東京都の約三分の一の5万ヘクタールは森林ということをご存知ですか?
平野部は都市化されましたが、多摩地域の傾斜地では森林が広がっていて、
その6割が植林で、そのほとんどが伐採の時期がきているとのこと。
ただ、写真のように30〜40度くらいのかなり急斜面に植林されているので、
搬出コストが高く、放置された山がかなりあるようです。
毎年、春になると悩まされる杉花粉。
東京の植林は歴史は浅く、戦後になってからだそうで、
山の頂上付近はモミと松、その下2割が檜、裾野あたりの7割が問題の杉。
実は伐採の時期を迎える樹齢30年くらい頃から急激に花粉が多くなるようで、
東京都は花粉対策として(その他、色々な理由があるそうですが・・・)、
10年程前から杉の伐採に力をいれているとのこと。
伐採後に植える杉の花粉は、伐採した杉の100分の1とのことですが、
その時期にならないと正確なところはわかないようです。。。。
枝はその場で落とした後、ある程度長さに切って、
ここから運び出すのですが、とても大変な作業ですね。。。。
ご存知の方も多いと思いますが、日本の林業は一部のブランド材を除くと、
外国の安い木材とは全く競争力がなく、森は放置されて荒れています。
東京都のようにお金のある自治体は、助成金で林業を支えることができますが、
日本全体としては深刻な状況です。
道路のある所に運び出された丸太は、その場で3mもしくは4mに切って、
トラックへ。
あちらこちらの山々から切り出された多摩産材は、
日の出町にある多摩木材センターへ集められます。
こちらは、木材市場に並べれた風景。
手前は太い丸太一本または二本毎で、次の列は6本から10本、
さらに奥は細い丸太が沢山積まれていますが、
それぞれを椪(はい)と言い、その椪ごとに競りをするそうです。
杉の丸太(手前の二本くらい)で1立米1万円、檜は2万円が相場で、
30〜50年手入れしてこの値段では全く林業は成立していないですね。
丸太から製材にする時に30%のロスがあり、その他乾燥で立米1万円、
人件費や輸送費など、コストアップしていくのは当然ですが、
最終的にはその5〜10倍くらいの値段となるようです。
そして、あきる野市の沖倉製材所へ。
まず、丸太の皮を剥く機械へ。
一往復すると・・・
こんな感じに!
さわると、とても湿っぽい水をたっぷり含んだ状態です。
皮、端材を燃やしてボイラーを動かし、
こちらの乾燥機で製材した木材を乾燥させます。
こちらは含水率とヤング係数を計る機械。
その値が、モニターに表示されます。
その値が刻印されて、
ようやく120角の柱材に。。。
植林してしからですと、とても長い道のりですね。
伐採してからここまでは4ヶ月ほどと意外と短い気もします。
いろいろと勉強になった一日でした。どうも有難うございました!