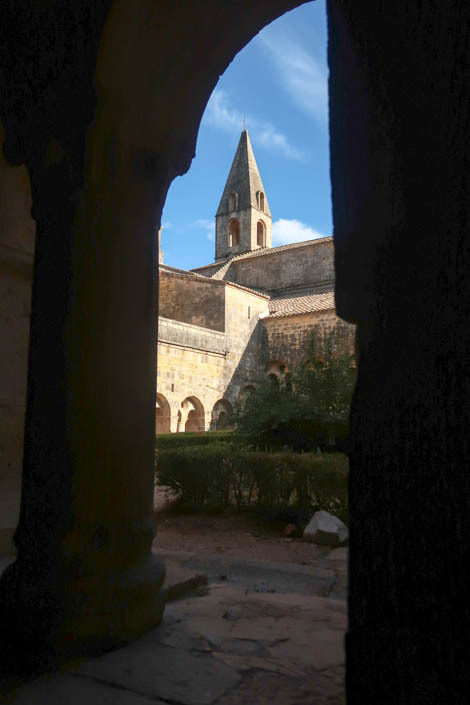伊豆長岡の三養荘に行ってきました。
建築界では誰もが巨匠と認める建築家の村野藤吾。世界平和記念聖堂や日生劇場などたくさんの名作があるものの、丹下健三などと比べて一般の方にはあまり知られていないのではないでしょうか?村野藤吾は近代建築の王道とは距離をとっていたので、今となっては歴史上の大きな文脈に乗らないので存在感があまりないのでしょうね。個人的には吉田五十八、堀口捨己と並ぶ近代以降の日本建築を設計する建築家として大変興味があり、三養荘は前々から見学したいと思っていました。
京都の「桂水園」やニューオータニの庭園内にある「なだ万本店山茶花荘」など村野藤吾が設計した作品にこれまでに泊まったり、食事をしたりしてきましたが、三養荘はそれらより敷居が高いイメージあったので、後回し(?)となっていました。今回は親の長寿のお祝いということで奮発!こんな機会ですから一番良い部屋を予約しました。
敷地面積は約42,000坪、東京ドーム3個分と広大。3000坪の広大な庭は7代目小川治兵衛、通称「植治」の作。元々、ここには三菱財閥の岩崎家の別荘があって、それらは重要文化財にも指定されています。それに加えて、昭和、平成の天皇陛下がお泊りになられた部屋が、庭を取り囲むように建っています。そして、その横の広大な敷地を買い足して、村野藤吾が新館を増築して今の三養荘となったようです。
まずこちらの広々とした車寄せに到着。ムクリのついた瓦の大屋根が美しいですね。大和、河内の民家に瓦葺きと茅葺きの二つの屋根で構成される「大和棟」と呼ばれるものがありますが、その「大和棟」を本歌とした2段の屋根が村野藤吾らしさの一つです。左側の塀は、南禅寺三門近くの山荘群の一つ「清流亭」と同様の栗ナグリ詰打ち仕上げ。その手前の竹は竪樋です。
エントラス横の照明。ハート形を崩したような形のこの「猪の目」の文様は、ここ三養荘ではもちろん、村野藤吾の作品のあちらこちらで見かけます。「猪の目」は古くは寺社、江戸時代以降はお茶屋さんなどで下地窓にも使われるようになった文様です。
扉を開けるとこのようなエントランス空間が広がっています。「忘筌」のように上部だけ障子を入れて、その先の庭も借景とてして取り込んでいます。天井の板をところどころくり抜いて、その奥から下向きの照明をとっています。
客室は起伏のある広大な敷地に地形に合わせて点在しているので、どこに行くにもかなり長い廊下を移動することになります。「雁行」しながら庭を眺めながら歩くので、次々にシークエンスが変わり飽きることはないのですが、旅館にしてはちょっと規模が大きすぎなような・・・・
滝があったり、小川が流れていたりと窓の外には様々な風景が広がっています。
庭の取れないところは、トップライトやハイサイドライトなどを巧みに使い、
明暗を作りながらも、先へ先へと誘います。
廊下の天井もよく見ると凝っていますね。
屋根が重なり合うように配置されています。
こちらはこちらは入れませんでしたが、エントランスを挟んで向かい側にある別棟。今年の秋から会員制の宿泊施設になるようです。村野藤吾が手がけた建物は広大ですね。
庭は明治の庭師、7代目小川治兵衛「植治」によるもの。「植治」と言えば、京都の無燐庵や平安神宮などの庭で知られていますが、それらの庭と比べるとこちらの庭は今一つハッとするようなところはなく、恐らく植治晩年のものでお弟子さんがかなりメインだったのでしょう。
「植治」の庭の周りには、三菱財閥の岩崎家の別邸が数棟配置されています。
文化財にも指定されている重要な建物で、こちらにも泊まれます。
本館の入り口はこのような感じ。
そして廊下です。
こちらの明治期の古典的な和風建築と比べると、村野藤吾の新館が近代以降の和の解釈をしていることがよくかわかります。
庭の高台に四阿。ここから、三養全体を一望できます。
こちらは宿泊客以外の方も入れるラウンジ。
天井は村野藤吾らしいデザインですね。